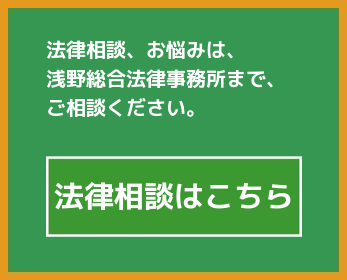就業規則を作成、変更することの企業にとっての意味とは、国にとって法律を改正することと同じです。
就業規則は、企業における法律、経営者の理念を社員におしえるための教科書にもなります。
適切な就業規則を作るには、どのような規定にしたらよいのかについて、何回かにわたって連載で解説していきます。
第1回目は「試用期間」についてです。
企業法務は顧問弁護士におまかせ!
顧問弁護士は、企業に日常的に起こる法律相談、契約書のチェック、労働者とのトラブルなどについて、経営者の味方となって戦うパートナーです。
適切な月額料金で、他の事務所より顧問弁護士を活用する方法について、企業法務の豊富な知識・経験を有する弁護士が、丁寧に解説します。
このページの目次
試用期間とは?
試用期間とは、企業が従業員を採用するときに、長期の雇用を前提として、採用する社員の能力、勤務態度などをチェックするために企業が設けるお試し期間です。
試用期間は法的に義務付けられているものではないですが、日本の労働法では本採用してしまうと解雇をすることが難しくなってしまいますから、従業員を採用する場合には設定しておいた方がよいでしょう。採用段階の数回の面接で、従業員の能力や適格性をすべて見抜くことは難しいでしょう。
そして、試用期間を設ける場合には、就業規則や労働契約書でしっかりと記載して従業員に説明しなければなりません
裁判例では、「留保解約権付労働契約」といわれています。この意味は、企業の判断によって、一定の場合には解約権を行使することを留保された労働契約という意味です。
試用期間の適切な長さは?
試用期間の長さに制限はありませんので、就業規則でも自由に決めましょう。
だいたい、1か月から6か月程度が一般的なのではないでしょうか。
ただ、試用期間は、解約権が留保されているという説明からもわかるとおり、従業員にとっては非常に不安定な地位に置かれることになりますから、長すぎると公序良俗違反を理由として無効と判断されることもあり、実際にそのように判断した裁判例も存在します。たとえば、ブラザー工業事件では、見習い社員期間(6か月から1年3か月)の後に、私用社員という身分で6か月から1年の試用期間を設定することは無効であると判断しました。
逆にいうと、1か月の業務ですべてを判断することもまた難しいといえますから、適切な長さは3~6か月程度と考えて就業規則を作成してください。
中途採用の場合には、年齢が高くなる分、健康状態に不安がある方もいますから、6か月などと長めに設定しておくとよいかもしれません。
試用期間についての就業規則の定め方の注意点
試用期間を設けるという場合には、就業規則か労働契約に定めた上で、労働者に対して適切に説明を行わなければなりません。
したがって、就業規則においてどのように定めるかが決定的に重要となってきます。
試用期間中の判断に関する規定
試用期間中であっても能力の判断をすることができ、本採用を拒否することができるようにしておく必要があります。
このような定め方をしなかったがために、「試用期間の終了時にしか適正を判断してはいけません」と考えられた結果、試用期間途中にどうしても能力不足であって早く辞めさせたいという場合であっても、試用期間中の解雇が違法と判断されてしまったケースもあります。
延長に関する規定
試用期間中に、従業員の能力や適格性を十分に判断することができなかった場合には、試用期間を延長することが企業側の判断として可能なように定めておくことが必要です。
ただし、就業規則に延長に関する定めをおいたとしても、何度も延長を繰り返すべきではなく、原則としては1回目の試用期間でしっかりと見極めるべきで、延長をすべきなのはごく例外的なケースに限られるでしょう。
また、試用期間の延長に関する規定があると、逆に従業員の側から試用期間を延長してもう少しチャンスを与えてほしいと希望されることがありますが、会社側の判断で延長をするかどうかを決定できるようにしておくべきです。
試用期間中の給料に関する規定
試用期間中は、通常の雇用の場合よりも少ない額の給料を提示する場合が多いでしょう。ただし、最低賃金を上回っている必要がありますので、注意が必要です。
以下の計算式でチェックしましょう。
試用期間の適用対象者について
試用期間は、長期的な雇用をすることを前提とした制度であるといわれています。
契約期間が短期間に限られている契約社員などの場合には、契約期間の満了と共に次の更新をするかどうかの判断をすれば十分で、試用期間を設定する必要性はあまり強くありません。
したがって、試用期間は、長期的な雇用を前提とした正社員のみに適用すべきですから、就業規則においても、正社員に適用される就業規則にのみ、試用期間の定めを置くべきです。
就業規則が1つしか存在しない場合には、パート、アルバイト、契約社員にはその就業規則が適用されない旨、または、少なくとも試用期間や休職などの長期的な雇用を前提とした規定の適用はされない旨の定めを置いておかなければ、「試用期間があるということは、ある程度長期的な雇用を前提としていたのかな?」と裁判所に判断されてしまうことにもなりかねません。
試用期間についての就業規則の規定例
最後に、試用期間についての就業規則の規定例を記載しておきます。
これはあくまでも例ですから、御社の状況に合わせて修正して頂く必要のあるものです。
第○条
1 新たに採用した従業員について、原則として、入社の日から3か月間を試用期間とする。
ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または、これを設けないことができる。
2 試用期間中及び試用期間の終了時において、労働者として不適格とみとめた場合には、解雇することがある。
3 試用期間の終了時において、労働者としての適性を判断できない場合には、第1項の期間を最長3か月間の範囲で延長することができる。
4 試用期間は勤続年数に算入する。
まとめ
以上のとおり、就業規則の規定に関する解説の第1回は、試用期間に関する規定の解説をしました。
企業の人事労務の担当者は、この記事を参考に、適切な試用期間となるよう就業規則を見直してみてください。
企業法務は顧問弁護士におまかせ!
顧問弁護士は、企業に日常的に起こる法律相談、契約書のチェック、労働者とのトラブルなどについて、経営者の味方となって戦うパートナーです。
適切な月額料金で、他の事務所より顧問弁護士を活用する方法について、企業法務の豊富な知識・経験を有する弁護士が、丁寧に解説します。